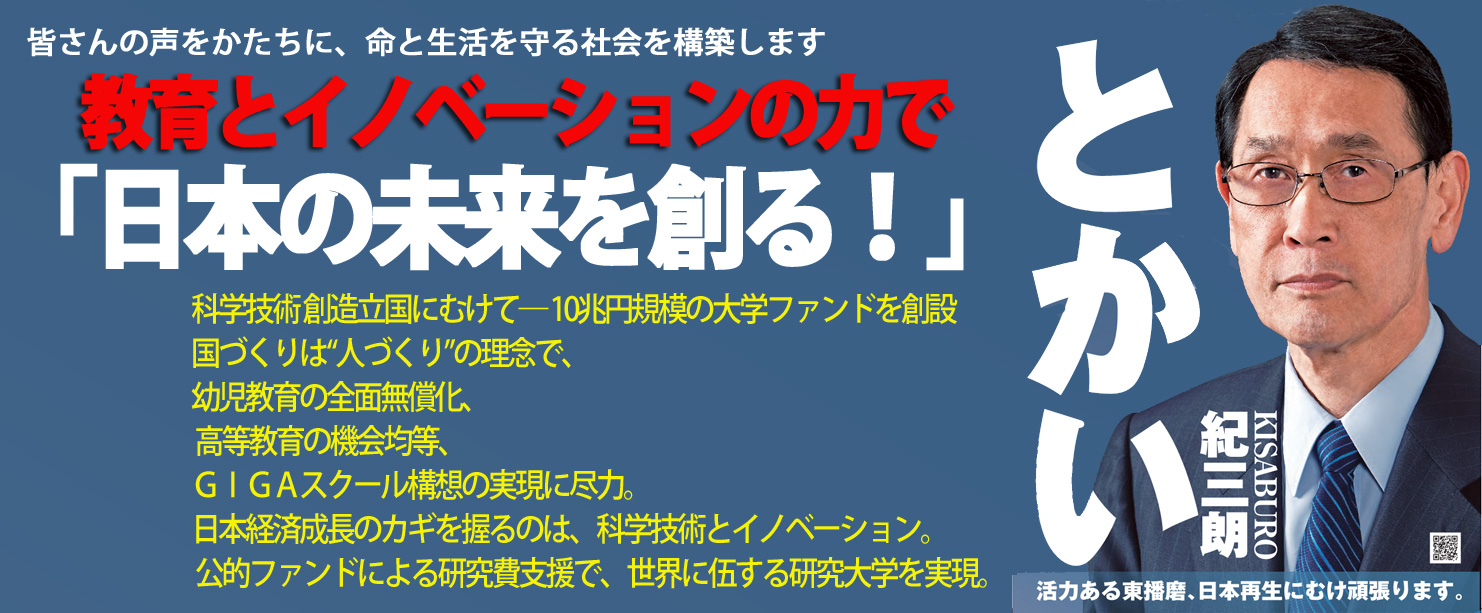「日本学術会議」の会員任命をめぐる総理の判断が物議を醸している。この会議は日本の科学技術を代表する機関であり、政府からの独立して職務を行う。法的には会員の任命は、会議が候補者を選考、推薦し、その「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」こととされている。会員の任期は6年、3年毎に半数が改選される。今回の改選分105人について菅総理は1日付けで、会議が推薦した新会員候補のうち6人を任命しなかったのだ。
この決定を受けて学術会議は、緊急に協議し、任命されなかった理由説明と改めて6人の任命を求める文書を総理大臣宛に提出した。
日本学術会議は科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的に、昭和23年(1948)に日本学術会議法が公布され、設立された。
かつて会員は科学者による選挙で選ばれていたが、昭和58年(1983)の法改正で登録学術研究団体を基礎とした推薦制が採用された。しかしこの手法では、団体代表が充て職のような形で会員となる例が散見されたため、再び平成16年(2004)に制度改正され、今日のように学術会議自体が会員候補者を選考する形式となった。
2日夕刻、総理は官邸を出る際に記者団に「法に基づいて適正に対応した結果だ」と述べているが…。任命手続きにおける総理の裁量権の有無については様々な意見がある。
確かに「会員の人事等を通じて一定の監督権を行使するということは法律上可能」かもしれない。しかし、推薦制を導入した昭和58年の法改正審議の際、政府は「学会の方からの推薦いただいたものは拒否しない。形だけの任命をしていく」と参議院の文教委員会で答弁しているのだ。
この経緯からすれば、今回の決定はこれまでの政府見解の変更となるので、変更理由の丁寧な説明が求められる。同時に、総理には6人を推薦しなかった理由についても説明責任がある。そうでなければ、科学者と政治の信頼関係を築くことはできず、科学的根拠による政策決定の実現に支障をきたすだろう。
一方で、この会議に毎年10憶円規模の国費を投じている以上、国民から選ばれた政治家による政治判断があってしかるべきだろうとの意見もある。これにも一理あるが、政治判断を行うのであれば、法令の改正も視野に入れる必要があるかもしれない。
新型コロナウイルス感染症対策を通じ、我々は政策決定における科学の役割の重要性を再認識した。国民の理解を得るうえでも、これからの政策決定にはエビデンス(証拠・根拠)に基づく科学的考察が必須である。そんな背景を受けて、私が会長を務めている党の科学技術・イノベーション戦略調査会の基本問題小委員会では、科学的根拠に基づく政策決定を実現するための議論を開始したばかりだ。日本を代表する科学者による政府の諮問機関である日本学術会議の在り方も、今後の中心的な検討課題の一つである。例えば、防衛技術と民生技術のボーダレス化に伴うデュアルユース研究などについては、考え方にかなり隔たりがあり、率直な意見交換を行いより良い関係を築こうと考えていた矢先での、今回の出来事である。議論に影響がなければよいのだがと、心配している。
“国民のために仕事をする内閣”と銘打ってスタートした菅内閣。着任早々総理は各閣僚に次々と具体的な改革方針の指示を出している。学術会議会員の任命方式の改変も、既存制度改革に向けた挑戦ということだろうか。
そうであれば、なおさら国民に分かりやすい対応が望まれる。行政手続きのデジタル改革、遠隔診療等の規制改革といった課題対応をスピード感をもって実行するためにも。
【デュアルユース】
科学技術は軍事利用と民間利用の境界はない。多くの国は、安全保障上の役割を理由に政府支援を実施している。学術会議は防衛省への科学技術協力を「軍事研究」として拒否。しかし、9割が軍事利用されると言われるレーザー技術に関するわが国のセミナーは他国の研究者が多数参加している。結果的に、自衛隊には協力しないが、最先端科学技術を他国群関係者に開放している状況だ。卑近な問題例である。