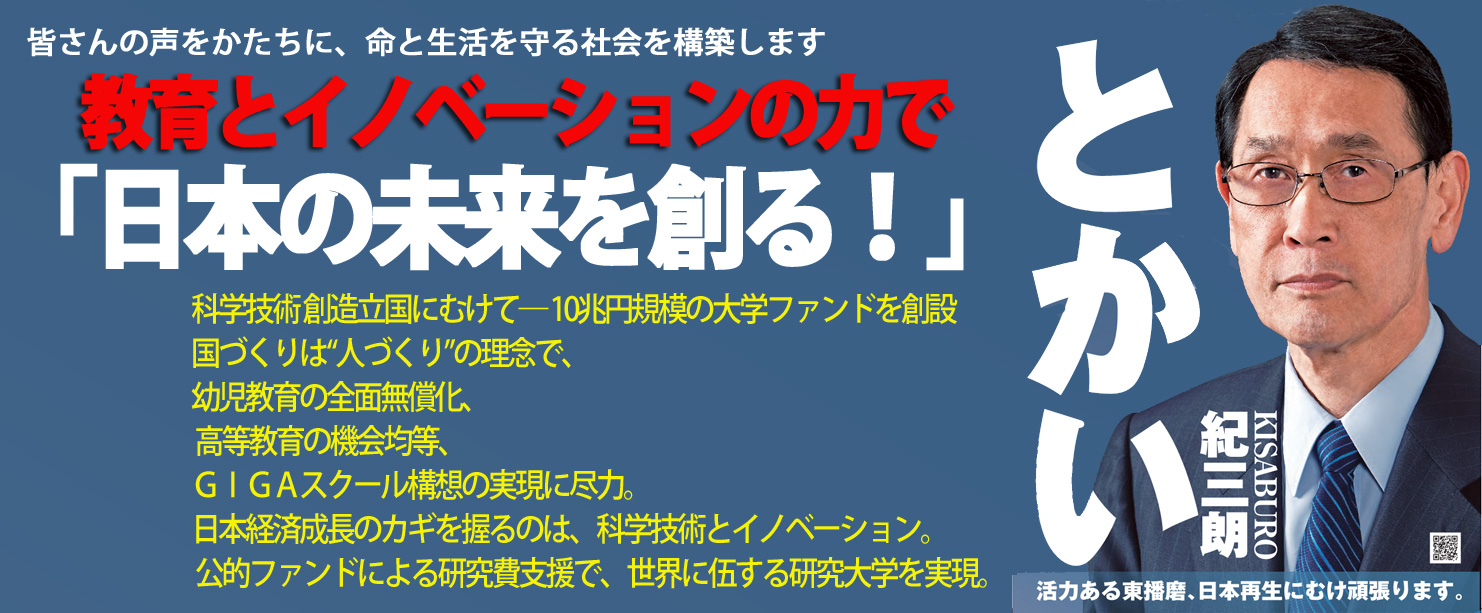自民党は23日、元復興相で無所属の平野達男参院議員(岩手選挙区)の入党を決めた。平野氏の入党で参院自民党の議席は122議席となり、参院で単独過半数を回復した。消費税導入やリクルート事件への反発で強い逆風の中での選挙となった1989年の参院選で過半数を割り込んで以来、27年ぶりとなる。
今回の平野氏の入党で自民、公明、おおさか維新、日本のこころの所謂「改憲4党」は、参院で162議席(諸派・無所属の改憲派を入れると166議席)を占め、憲法改正の国会発議に必要な3分の2議席を衆参両院で確保することとなった。
さて、前回のコラムでも言及した憲法改正を巡る議論。
「改憲勢力が2/3になったら、安倍総理は必ず9条の改正をやる」とまで言い切り、改正阻止を前面に押し出し、「改憲勢力による2/3確保阻止」を勝敗ラインにあげて参院選を闘った岡田民進党代表だが、選挙後の発言はいささか趣が違っているようだ。
「安倍政権下での憲法改正議論に反対」と主張していた岡田代表は、参院選後「憲法改正、あるいは議論そのものを一切しないと言っている訳ではない」と言及。改憲勢力に2/3を許したことについても、「何が2/3か、いろいろな考え方がある」と、開き直ったかとも思える発言で責任論を回避している。
岡田代表の責任論は民進党の皆さんが9月の代表選で総括すればよいと思うが、条件付きとはいえ、憲法改正の国会での議論に道筋が開けたといえる。
秋に予定されている臨時国会では、今後の進め方も含め活発な議論がおこなわれることを期待する。
憲法改正議論は、各党が改正を必要と考える条文についての意見を持ち寄り、論点が明らかとなった項目からスタートすべきであろう。憲法改正と言うと9条に焦点が当てられるが、改正を議論すべき項目は数多くある。
緊急事態条項や環境権など、70年前の憲法制定時には想定されなかった新しい項目。おおさか維新が提起している統治機構の問題、あるいは衆参両院のあり方や参院の選挙制度の問題も俎上に載せる必要がある。前文も、より美しくわかりやすい表現に改めてはどうだろうか。
その他、53条(臨時国会召集)や89条(公金の使用)、96条(改憲手続き)などについても議論が必要だ。
なかでも私が最も重要視しているのは83条(財政)だ。83条には「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない」と規定されているが、財政についての責任が不明確である。憲法改正に当たっては、前項に加え「国は国家の財政に責任を持たなければならない」という、新たな項目を加えるべきというのが従来からの私の主張である。
自民党が“憲法改正草案“を提示してから早や4年が経過した。草案策定後に選出された議員も数多くいる。秋からスタートする国会での議論を前に、党内でも草案内容の見直しや優先順位をめぐり議論が活発化するだろうが、私は83条の改正を強く主張するつもりだ。
憲法改正は、まず国会議員により改正原案が提案され、衆参各議院の憲法審査会で審査のうえ、本会議に付される。そして、両院がそれぞれ2/3以上の賛成で可決された場合、国会から国民に対しする提案が行われ、国民投票による過半数の賛成で承認、決定される。
今後、国会議員による改正原案策定の議論がよりオープンな形で行われることにより、国民の間でも憲法改正についての理解が深まることを期待する。