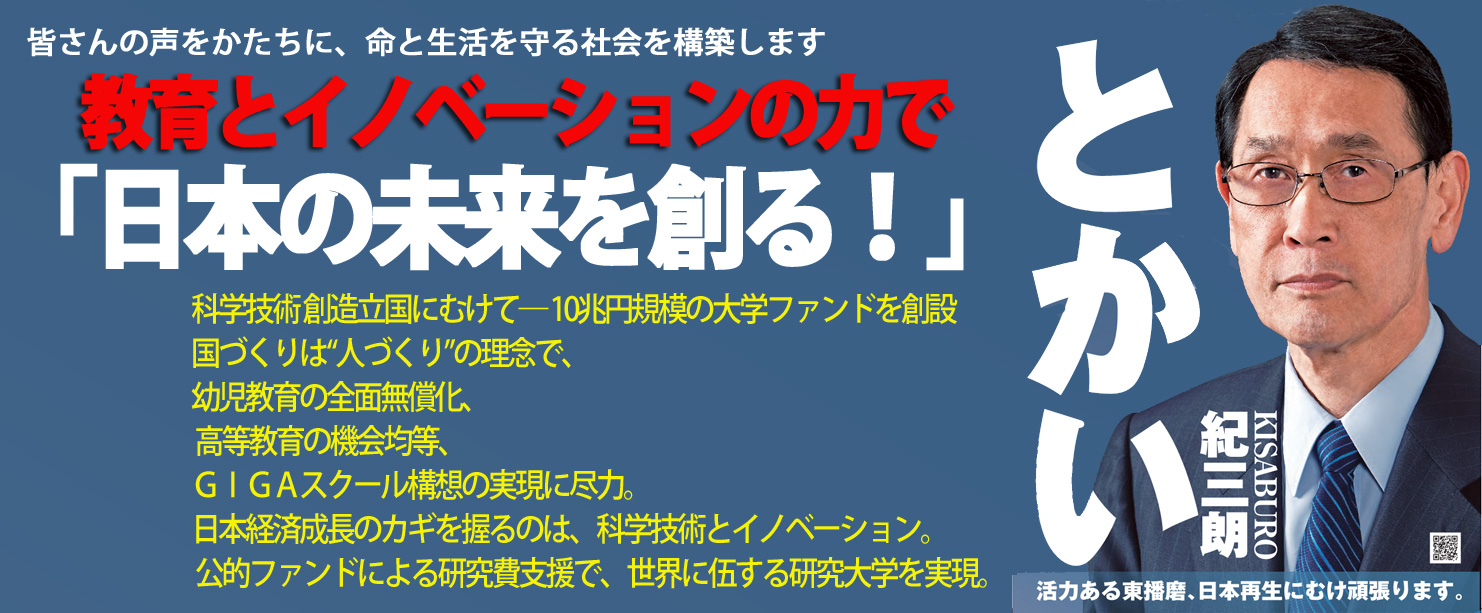平成28年(2016年)の申年もあと数日。恒例の今年の世相を表す漢字は、オリンピックの年らしく「金」が選ばれた。「金」は2000年のシドニー五輪、2012年のロンドン五輪の年に続き3度目となる。
オリンピックの舞台となったリオは、日本から見ると地球の真裏で時差は12時間。朝と夜が逆転する。日本中を睡眠不足に陥れた17日間、日本は金12個に銀8個と銅21個の計42個という過去最高のメダルを獲得した。その期間(8月5日~21日)はちょうど国会が夏休み、地元スケジュールの調整も比較的容易で、私も思う存分TV観戦することができた。
勝利して感極まって流す涙もあれば、敗れて流す悔し涙もあった。日の丸を背負って大活躍し、私たちに大きな感動を届けてくれた選手たちに改めて拍手を送りたい。
オリンピックと言えば、2020年の東京大会の施設整備や運営方法について国、東京都、組織委員会の間で協議が行われている。費用負担を巡って議論が紛糾しているようだが、一日も早く問題を解決し、大会成功に向けて力を結集して頑張って欲しい。
私は今年もライフワークである科学技術政策を中心に活動をしてきた。
党科学技術・イノベーション戦略調査会長として、4月には一億総活躍社会実現の旗印の下、科学技術振興をアベノミクスの大きな柱の一つと位置づけた。予算編成の季節は、「科学技術は未来への先行投資」と訴え、新規・拡充予算の獲得に奔走した。その成果として、歳出抑制の基調のなか、科学技術振興費はかろうじて0.9%の伸びを確保できた。
秋の日本人のノーベル賞受賞ニュースも年中行事となってきた。今年は大隅良典先生が昨年の大村智先生に続き、生理学・医学賞を受賞された。受賞決定後の早い段階に科学技術・イノベーション戦略調査会に出席いただく機会に恵まれたが、先生からは「若手研究者が十分に研究に取り組める環境の実現」を求める言葉が繰り返された。
そう言えば2012年に、iPS細胞で生理学・医学賞を受賞された山中伸弥先生も「日本は科学が国を支える柱、ぜひ多くの若者たちに科学者になって欲しい」と言っておられた。
日本の未来を切り拓く上で、人材の育成は大きな課題である。
その意味でもこの3カ月間、与党のプロジェクトリーダーとして、大学生を対象とする「給付型奨学金」の制度設計に取り組んできた。
学ぶ意欲と能力があるのに、経済的事情で大学進学を諦めざるを得ない子どもたちの一助になればと願っている。今後もこの課題に全力で取り組む所存である。
今年は世界が大きく揺れ動いた一年でもあった。
英国では6月にEU離脱の是非を問う国民投票が行われた。その結果は、予想に反するEU離脱派の勝利に終わり、キャメロン英首相が辞任に追い込まれた。
米大統領選挙でも大半の予想を覆し、共和党のドナルド・トランプ候補が民主党のヒラリー・クリントン候補に勝利。トランプ氏は来年1月20日には合衆国大統領に就任する。
米英両国とも既存秩序体制(エスタブリッシュメント)に対する大衆の不平・不満が底流にある。全世界の経済活動が一体化し、(移民も含め)人の移動も容易となる一方で、移民排斥をはじめとする排外主義的思想の拡大は気にかかるところである。
今年から来年にかけて、昨春伊勢志摩に集ったG7メンバーが相次いで、その座を退くことになる。すでにキャメロン英首相が去り、レンティ伊首相も退陣。オバマ米大統領は間もなく任期を終える。オランド仏大統領も来春の再選に不出馬を表明した。以上で7人中4人が交代。さらにドイツでは、秋に連邦議会総選挙が予定されているが、メルケル独首相の支持率は難民施策を巡って低迷している。
サミットにおいて古参となる安倍総理の地位は当然高まるだろう。そして、その言動はG7の動きを左右するのではないだろうか。日本が国際社会でリーダーシップを発揮するためにも、国内政治の安定が求められる一年になりそうだ。
今年も私どもの政治活動に対してご理解ご協力を賜り、有難うございました。
来年も引き続きご支援ご鞭撻をお願いします。良い年をお迎え下さい。