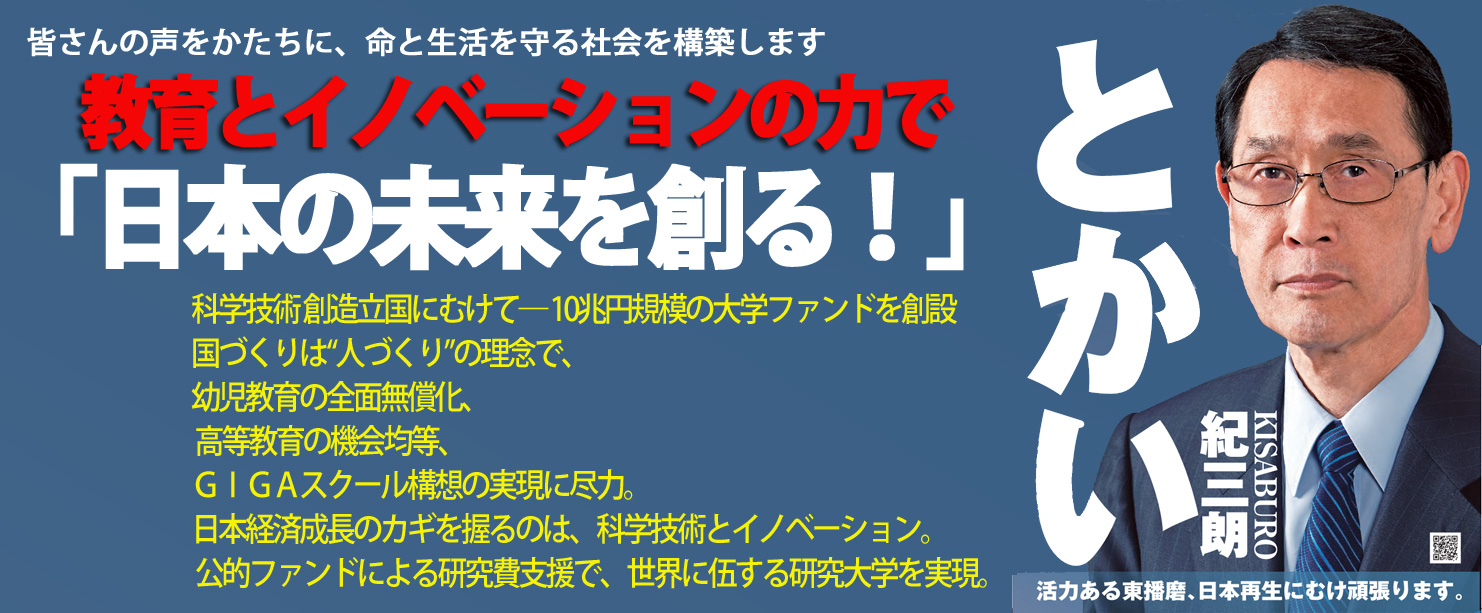今年の大河ドラマ「軍師官兵衛」は、いよいよ前半のクライマックス。有岡城幽閉から三木城攻略戦へと展開していく。しかし、この直前の東播磨諸城の戦いついては、準主役の“光”のふるさと志方城の落城があっさりと描かれたのみで終わってしまったのが少し残念な気がする。
ドラマでは当然ながら主役である官兵衛側の論理で播磨平定が描かれている。だが、加古川流域に暮らす住民からすれば、何の罪もない祖先のふるさとが織田軍に蹂躙された悲劇の時代とも言える。なかでも神吉城(加古川市東神吉町)は、わずか2千の兵(わずかと言っても当時の人口からすれば一大勢力)で織田信忠率いる3万の軍勢を良く防ぎ、20日も籠城戦を続けた後に、ほぼ全員が討ち死にしたという。
「播州太平記」によると、この善戦は城主神吉頼定の鬼神の活躍によることとされているが、その活躍を助けた要因の一つは加古川の流れだろう。当時の加古川は暴れ川で、神吉集落の南側は、三角州のような状態。多数の中小河川が複雑に蛇行しながら流れ、毎年のように流路を変える地域であったらしい。故に神吉の城は南を湿地帯、北は山地に守られた要害だった。いかに3万の大軍とはいえ、一斉に戦力を動員し、力責めをするのは難しかったのであろう。
この加古川の流れを現在の形に治める工事を始めたのは江戸時代の前半。姫路藩主榊原忠次の命により升田から船頭へと続く升田堤を築造し、流路を整えた。しかし、この堤防は明治時代にかけて何度も決壊し、加古川右岸は度々大水害に見舞われた。現在のような安定した堤となったのは昭和以降の話だ。
かつての暴れ川の歴史は、地名に残る。加古川左岸の中津、河原、粟津、右岸の出河原、岸、島、中島等々、今や町並みや田畑が広がる地域に水にゆかりの名前が続く。
加古川市・高砂市に限らず、日本の都市の多くは大河川下流域の沖積平野に広がっている。
つまり、豊かに思える我々の生活は常に水害の危険に晒されていると言うことでもあるのだ。加古川の河川整備基本方針が想定する水害は、明治時代以降のみ。150年に1回の大水害に耐えられる水準で整備が進められている。加古川の事業が遅れているわけではない。全国の多くの河川は、100年に1回の水害にも耐えられない。
3年前の東日本大震災の巨大津波ではないが、仮に播州地域が千年に一度の集中豪雨に見舞われ、加古川本流の堤防が切れるようなことになれば、濁流は加古川、高砂の平野部を呑み込む。市役所が作製しているハザードマップを見れば一目瞭然。別府川と法華山谷川で囲まれた地域の大半が0.5m以上の浸水域となっている。
避難が必要な災害は、津波だけではない。我々の都市は古来より水を治めながら拓いてきたということを常に認識し、万が一への備えを怠ってはならない。
400年前、圧倒的な織田軍団に、あえて戦いを挑んだ播州人。加古川の流れは変われども、故郷のためには強大な苦難にも立ち向かう播州人の気質は変わらない。
私にもその血が流れているのだ。国会終盤に向けて、TPP、安全保障問題等々、国政には課題が山積している。流れにさおさすことなく、時代潮流を自ら冷静に分析し 自説をしっかりと主張していかなければならないと、改めて思う今日この頃だ。