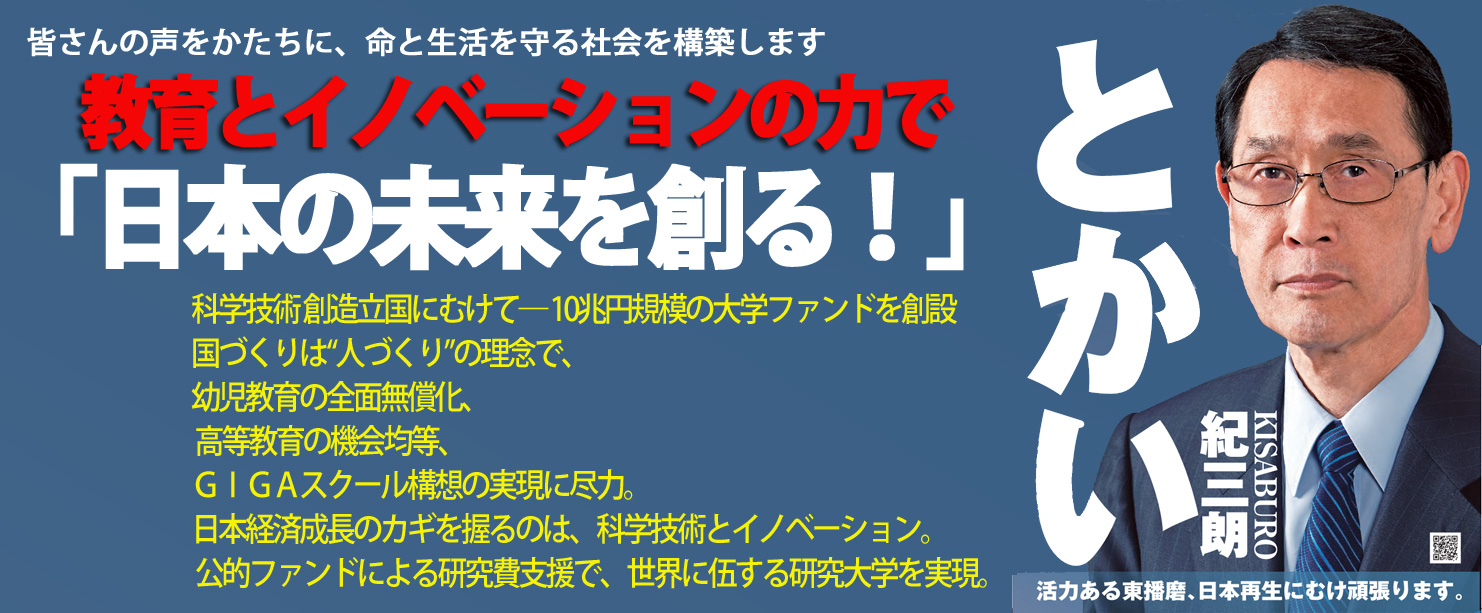先週の20日、安倍内閣の重要政策の一つである教育委員会制度改革を具体化する“地方教育行政法改正案”が、衆院本会議で可決され参院に送付された。今国会での成立は、ほぼ間違いない。
昨年末の「教育委員会改革に関する小委員会」委員長就任以来の長い道のりを振り返ると、苦労して育ててきた子どもが巣立っていくような感慨を覚える。
六十数年前の戦前の教育は、他の行政分野と同じく中央省庁が全国画一の制度内容を定め、地方の府県知事や市町村長は単に事務を執行する役割であった。
これを地方主体の自治システムに転換しようとしたのが現在の教育委員会制度のはじまり。昭和21年3月にまとめられた米国教育使節団の報告書をベースに、GHQの勧告で設置された教育刷新委員会で現行制度の原型となる学制改革案が提言された。こうして昭和23年に定められた教育委員会法により、初等・中等教育においての地方分権と教育への民意の反映を目的に、公選委員による独立性の強い教育委員会制度(後に現在の任命制となる)が設けられた。アメリカ方式の住民主体の行政委員会制度だ。
制定から60年、数次の制度改正はなされたものの基本形は維持されてきた。しかし、2011年に発生した“大津市いじめ自殺事件”に際しての教育委員会の無責任な言動や場あたり的な対応を契機に、迅速性に欠ける合議制の意思決定、名誉職化した委員選考、事務局の閉鎖性といった委員会制度の根幹に係る問題点がクローズアップされ、戦後教育の総決算ともいえる教育委員会制度の抜本改革が喫緊の課題となった。
改革案作成を諮問された中央教育審議会は、昨年12月、教育行政の最終権限を自治体の首長に移管する案と、従来どおり教育委員会に残す案の両論を併記する形で文部科学大臣に答申した。通常、このようなケースでは審議会の答申がそのまま改正法案の原型となる。しかし、今回は、案を一本にまとめきれなかったということだ。それほどに戦後教育の総決算は難しい。
一本化の作業工程は、政治の手に委ねられることとなった。法案提出に至るには、まず答申を踏まえた自民党案を作り、それを土台に公明党と調整して与党案を策定しなくてはならない。しかし、自民党内でも様々な意見があり、政高党低(官邸主導)に対する感情的な反発も含め、一筋縄ではいかない状況であった。
そんな状況下で、自民党文部科学部会に設置されたのが、先に触れた「教育委員会改革に関する小委員会」。即座に下村大臣をはじめ文教関係議員幹部から委員長就任要請があった。「文科大臣経験者で、ニュートラルな立場でこの件の取りまとめに臨めるのは渡海さんしかいない」と、何度も繰り返し要請されたのだ。
1月9日にスタートした小委員会は、甲論乙駁の議論が白熱したが、週1回のペースで議論を重ねるとともに、コアメンバーによる論点整理や新提案も繰り返し、2月19日には部会での了承を取り付けた。翌20日には、公明党とのワーキングチームの座長に就任し、与党案作成に向けた会合がスタート。3月12日になんとか合意に至った。
政府による法案作成を経て、4月15日の衆院本会議に上程された地方教育行政改正案の委員会審議は、42時間55分という異例の長時間審議を経て、5月16日に採決、そして冒頭の衆院通過となった。
法案の主な内容は、
①首長が教育長と教育委員長を一体化した新たな「教育長」の任免権を有する。任期は3年。首長の教育行政への権限強化と責任体制の明確化を図った。
②原則公開の首長が主宰する「総合教育会議」を新設し、教育行政の大綱や条件整備について協議・調整する。特に生徒の生命または身体保護等の緊急事態対応を含む。
③教職員人事や教科書の採択等の執行権限は、教育委員会が保持し中立性を保つ。
というもの。基調をなすのは、「教育行政の責任の明確化」「学校の危機に迅速に対応できる体制」である。
原案どおり法案が成立すれば平成27年4月の施行となる。この制度改革は枠組みを作り直したに過ぎない。日々教育内容を見直し、現場で発生する種々の課題解決を図るのは、各地域の住民の方々と自治体の力だ。新たな枠組みのもと、地域の創意工夫で、理想の教育が形作られることを期待している。